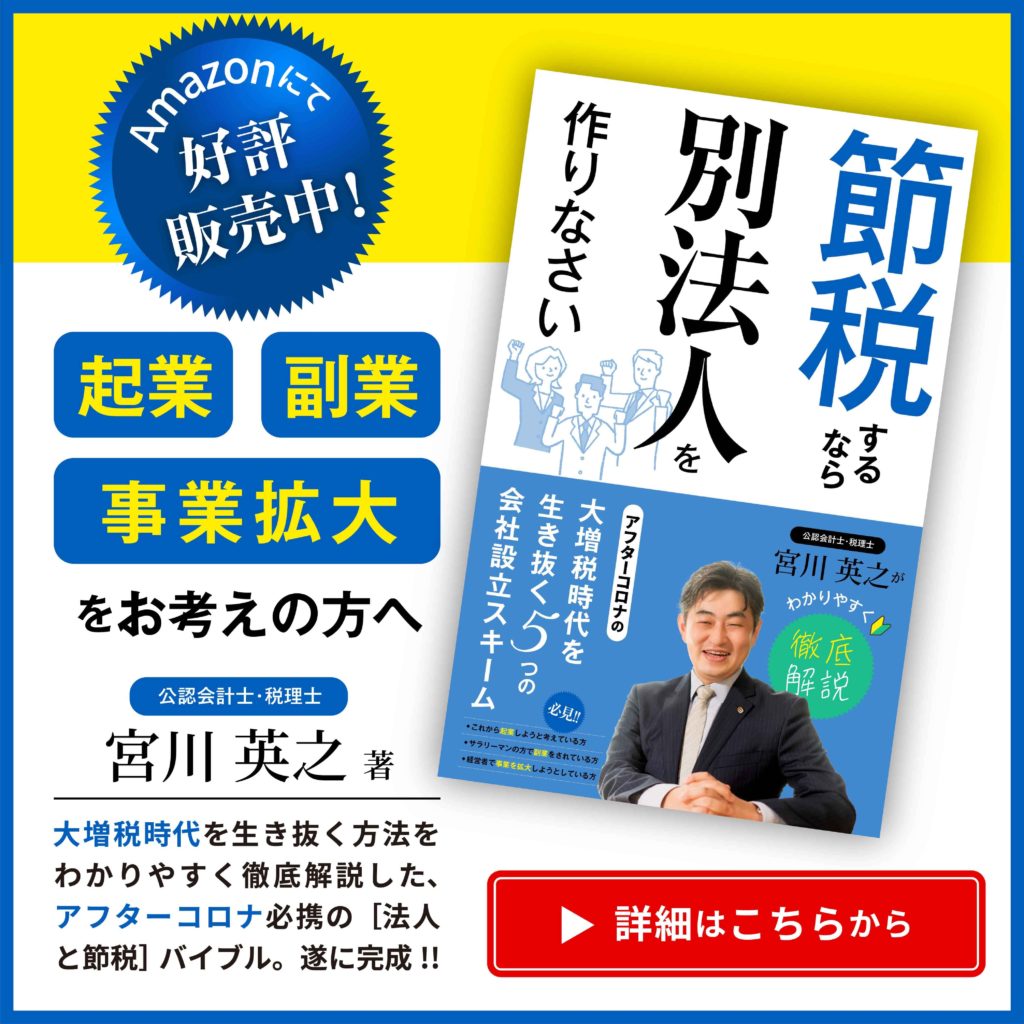「会社設立か個人事業か?」の決断を導く9つの視点
会社設立時に慎重に考えべき法人の利点

起業時に「個人事業」にするか、それとも会社設立して「法人」で経営するかで迷う方も多いと思います。法人になると、いわゆる社会的信用が増し、大きな企業との取引がしやすくなったり、金融機関からの融資が受けやすくなったりすることもあるでしょう。逆に法人化のデメリットはないのかも心配になるでしょう。
ここでは、会社設立して法人化した場合の主なメリット、デメリットを簡単にご紹介します。
法人化メリット① 「家族の給与」
個人事業の場合、所得税や住民税などは、大まかに言うと、「実際の収入(売上高)」から「必要経費」や「所得控除額」を差し引いた「課税所得」に対して課せられます。
ですから事業運営において節税のメリットを受けるには、「経費として計上できるものはできるだけ経費に」、「利用できる所得控除はできるだけ利用」するのがポイントです。法人の場合にも、基本的には売上から費用を差し引いて計算します。
起業に当たり、「妻(または夫)」や「親、あるいは子供」に事業を手伝ってもらい、給料を支払う場合は、「法人化」すると節税ができるケースもあります。
これは、配偶者や子供に働いてもらいながら、税制上の「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられるからです。
まずは「配偶者控除」についてです。そもそも所得税などの課税額は、収入から一定額を差し引く(控除した)額に税率をかけて算出されますが、このうち「配偶者控除」とは、「妻(または夫)を養っている納税者に対して、税負担を軽くしてあげよう」という趣旨なのです。
例えば、起業時に法人化して、一緒に働いてくれる妻に給料を支払う場合は、奥さんに支払った給料は会社の費用として扱うことが可能です。
その上で、奥さんの給料の年額が103万円以下なら、納税者である夫が「配偶者控除」の対象になるため、夫の収入から「配偶者控除」分の38万円を差し引いた額に、所得税が課税されることになり、節税になります。これは、個人事業で青色事業専従者給与の届出書を提出して実際に支給すると、配偶者控除や扶養控除の適用は受けられなくなるためです。
個人事業で開業し、「生計を一にしている妻(または夫)への給料」を「経費」と認めてもらうには、税務署への届出が必要です。また、そうした妻(または夫)に対し、年に1度でも給料を支払うと、その給料の額に関係なく、配偶者控除の対象にはなりません。
「なぜ!?」と疑問にお思いになりますが、それが税法上の取り扱いなのです。つまり個人事業では、「妻(または夫)に給料を支払うか」、或いは「給料を支払わずに、配偶者控除を受けるか」のどちらかを選ばなくてはならないのです。
同じように「生計を一にする親や子供」など「扶養家族」に事業を手伝ってもらい、給料を支払う場合も、法人であれば「扶養控除」の対象になりますが、個人事業では扶養控除の対象になりません。
ただし「配偶者控除」も「扶養控除」も、対象になるには「生計を一にしている」ことなどの所定の条件です。
法人化メリット②「欠損金の繰越控除」
いざ開業したものの、最初の数年間は赤字が出ることもあるでしょう。「赤字」のことを会計の専門用語で「欠損金」と言いますが、「その欠損金(赤字)を翌年度以降に持ち越して、黒字になった決算期に相殺することで、課税所得を少なくしてあげましょう」というのが、「青色欠損金の繰越控除」の趣旨になります。
「青色」とは確定申告の際の「青色申告」のことを指します。確定申告には、家計簿を付けるような単式簿記で申告する「白色申告」と、事前に届け出た上で複式簿記での帳簿付けが必要な「青色申告」の2種類がありますが、このうち「青色欠損金の繰越控除」の対象になれるのは、文字通り、「青色申告をしている事業者」だけです。
この「青色欠損金の繰越控除」は繰り越せる期間が限られていて、個人事業の場合は3年間ですが、会社の場合は9年間繰り越すことができます。
例えば創業から毎年100万円の赤字が出て、数年後に1000万円の黒字が出た場合などに繰り越した赤字を黒字と相殺することができるのです。
なお、平成27年の法改正により、平成29年4月1日以後の事業年度は、法人に対する「青色欠損金の繰越控除」の期間がさらに伸びて、10年間となります。個人事業と比べてさらに有利です。
法人化メリット③ 「退職金」
前述のように、事業収入から経費を差し引き、課税所得をできるだけ圧縮することが節税のポイントとなります。そのためにも、経費として計上できるものは経費にしておくことがポイントです。この点、会社を作れば、「社長である自分自身や従業員に支払う退職金」を経費として計上することも選択肢として考えられます。
「退職金」には「退職所得控除」という制度があり、退職後の生活も考慮されて税制上は有利な取り扱いになっています。
一方、毎月の給与には、社会保険料や所得税、住民税などがかかります。そこで、「毎月の給料を減らしてでも、退職金として支払った方が、税金や社会保険料が安くなる」という利点があります。
しかし、個人事業では、「個人事業主から個人事業主に対して、退職金を支払う」という考え方が成り立たないので、原則的には退職金を経費とすることができません。
法人化のメリット④「経営者の生命保険料」
続いて「経営者の生命保険料」についてです。
経営者が死亡した場合の事業継続に備えて、個人事業で、経営者の生命保険を年間いくら支払っていたとしても、「生命保険料控除」として控除できる額は、規定上最大金額が決まっています。
一方、会社設立して法人化した場合では、法人名義で社長に対する生命保険料をかけ、受取人を法人にした場合は、その生命保険料の全額または一部を経費化できるので節税につながる余地もあります。
法人化のメリット⑤「出張旅費、社宅家賃など」
事業経費の大きな割合を占めることが多い事業所家賃はどうでしょうか。
個人事業では、自宅家賃のうち、事務所としての業務にかかる部分のみの割合を計算して、経費として申告します。これを家事あん分と言います。
一方会社では、会社が住居を借り上げて、それを「社宅」として取り扱うことによって、状況にもよりますが、家賃の住居部分の概ね50%を費用とすることも可能です。
この他、会社設立して、会社の社内規程を定めておけば、「出張日当」や「慶弔金」を経費にすることも可能な場合もあります。
法人化のデメリット①会社が赤字でも法人住民税を支払わなくてはならない。
個人事業でも法人でも、事業を行っていれば、所得税や住民税、事業税などを納めます。
しかし個人事業の場合、事業が赤字で課税所得がゼロの場合、所得税や住民税、事業税など税金はかかりません。
一方法人は、事業が赤字で課税所得がゼロの場合、法人税と法人事業税はかかりません。しかし「法人住民税」のうちの「均等割」という税金だけは、例え赤字でも、毎年固定費として払わなくてはなりません。この点、法人は必ず税金の支払が発生することになります。(ただし、法人の赤字は最大9年間繰越することも可能です。)
法人住民税は、都道府県と市区町村に支払う税金で、「会社がこの場所にあるのだから、わが地方自治体にも相当の負担を支払ってください」というような意味合いのものです。税額は、自治体や資本金の額などによって違いますが、例えば、
福岡県の場合、資本金等の額が1000万円以下の法人で、年額21000円、
福岡市の場合、資本金等の額が1000万円以下で、従業員数が50人以下の法人で、年額5万円
なので、福岡市で会社を経営している場合には、最低でも合計7万1000円を支払わなくてはなりません。(事業期間1年の場合)
法人化のデメリット② 会社設立時の登記費用、設立後も手間
個人事業を開業する際は、開業届けを税務署に提出すれば済みますが、株式会社を設立するには、定款認証や法人設立登記などの費用として、ざっと20~30万円がかかります。
また、会社設立後も、個人事業で白色申告の場合は、毎年1~12月までの売上や経費を集計して、税務署で不明点を尋ねながら、翌3月15日までに確定申告をすれば済みます。慣れない方でも頑張れば自力で済ますことも可能でしょう。
一方会社設立した場合、メリットの多い青色申告で確定申告するのが一般的です。その場合には、日々の取引を複式簿記で記帳すると共に、決算期末から2ヶ月以内に、決算報告書などを税務署に提出しなくてはなりません。
多くの場合、会計事務所などのサポートが必要になり、その場合はもちろんサポート料も支払わなくてはなりませんが、そのサポート如何では、サポート料以上の節税効果や経営支援を受けられる場合もあります。
法人化のデメリット③ 社会保険料負担
会社を作り、社長自身や家族従業員、またはそれとは別に雇い入れた従業員が「健康保険」「厚生年金保険」に加入する場合は、それぞれの保険について、会社負担分の保険料を支払わなくてはなりません。
労災保険は、全額会社の負担です。雇用保険は、従業員と会社の両者で負担しますが、会社の負担率がやや大きくなっています。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、都道府県ごとに違いますが、保険料の負担は、従業員と会社で折半です。
法人化のデメリット④ 交際費
個人事業では、接待にかかる飲食代や贈答品など、基本的には必要経費として認められます。しかし法人では、例えば中小法人の場合、現行の税制では、交際費の上限が1年間で800万円と決まっています
 Previous Post
Previous Post Next Post
Next Post